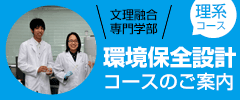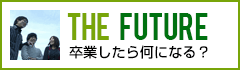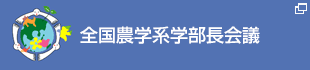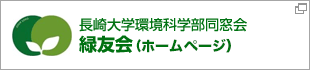受講案内
卒業研究の紹介
平成30年度卒論題目
環境政策コース
●日本版CCRCにおける地域交流拠点の特性と活用に関する考察
●長良川最上流域における森林整備による生物多様性と水源涵養・洪水緩和に関する受益意識について
●手仕事が紡ぐ人々の居場所―「移住したいまち」福岡県糸島市のハンドメイドの世界から―
●2020年のデジタル教科書導入に伴う環境負荷シナリオ解析
●漂着ごみ問題の改善と観光収入の増加を目指した入島料徴収の検討
●九州地方における、シカとイノシシの獣害の実態と食肉利用について
●平成29年九州北部豪雨災害時の避難行動の特性に関する分析~花月川流域の住民を対象として~
●市町村間連携による移住・定住政策の効果に関する研究―空き家バンクに着目して―
●「ご当地エネルギー」の構築過程とローカルガバナンス―大分県竹田市自治体新電力の創出を目指して―
●浮体式洋上風力発電に関する研究
●長崎市における観光PRに関する研究―観光PRの諸事例の比較から―
●地方中核都市の大規模住宅地における商業施設の変遷
●水辺に立地する公園の着座装置における行為と周辺環境の関係
●低炭素と健康増進の両立に向けた食のライフスタイルの考察
●日本の地域別ライフスタイル由来のカーボンフットプリント解析
●若年層の都市部への人口流出に関する経済学的分析
●九州新幹線西九州ルートの効果に対する在来線利用者の意識の考察
●大学生における都会志向・地元志向の考察―長崎県を事例として
●地方都市における近隣型商店街の店舗構成と取り組みの変容に関する研究
●高齢者向けのバス停環境の整備実態
●陶磁器職人の生活史から読み解く地域形成の現在~陶磁と緑のまち波佐見町を事例に~
●高齢者を対象としたユーカリプトルの香りの有用性
●民泊の現状と今後のあり方について
●日本における環境教育の充実に向けた提言―学校教育での取り組みを中心に―
●ソーシャル・ネットワーキング・サービスの〈コミュニケーション疎外〉とその可能性について
●微細藻類由来のバイオディーゼルの経済性・環境効果とその展望
●日本におけるヴァーチャルパワープラント構築の可能性に関する考察
●小型家電リサイクル法の施行状況と課題に関する考察
●AI農業は何を不可能にするか?―農業の人間的価値の考察
●風力発電適地選定プロセスに関する研究
●地方中核都市における無電柱化事業の実施実態
●生業の垣根を越える南小国町地域づくりの試み~黒川温泉の産業間連携の取り組みから~
●耕作放棄地拡大の要因分析
●震災瓦礫の仮置き場所決定に関する要因分析:熊本地震を事例として
●日本におけるユニバーサルツーリズムの現状と課題―沖縄の事例を中心に―
●光害を通して考える光と私たちの関わりのこれから―熊本県民天文台の取り組みを中心として
●世界遺産・屋久島におけるエコツーリズムと環境保全政策に関する研究
●静岡市における再生可能エネルギーの地産地消政策の批判的考察
●有機食品に関する日独比較研究
●石油性プラスチック廃棄物による環境負荷と今後の対策
●「遊び」から余暇活動のあり方を考える―人間-自然関係の充実に向けて―
●軍艦島の保全と観光利用について
●森のようちえんの現状と課題―長崎よかよか塾を事例として―
●立地適正化計画と都市計画区域マスタープランの関係に関する研究
●プロスポーツによる地域活性化の課題と可能性―V・ファーレン長崎とそのホームタウンを事例として
●日本に適した地熱資源のコミュニティ利用とは~4地域の事例比較に基づく考察~
●国立公園内の希少植物の保護について
●ESCO事業の現状と推進方策について
●ジビエを産業として成り立たせる条件とは何か―長崎県を事例として
●持続可能なエネルギー利用―廃棄ソーラーパネル処理対策について―
●長崎における世界遺産登録と観光のあり方に関する研究―長崎県および長崎市への聞き取り調査から―
●中国の豪雨災害に関する相対的リスクマッピング
●中国・武漢市におけるシェアバイクの実態把握と課題に関する考察~大量廃棄の原因解明に向けて~
●環境アセスメントにおける生物多様性の保全
●軍港都市・佐世保の戦後―海上自衛官にとっての地域社会
●長崎のキリスト教関連世界遺産に関する一考察
環境保全設計コース
●デルタ前縁海底の水深が支配するデルタ分流チャネルの動態:水槽実験
●セイロンシナモン熱水抽出物がラット学習記憶能に及ぼす影響評価
●有機合成化学的手法による二酸化炭素の有効活用
●雲仙市における地下水の水質分布特性について
●オキチモズク室内培養藻体の川出しの試み
●長崎県で採取された越境大気に含まれるイミダゾール類の分析
●腐朽菌を用いた分別土中木くずの分解
●不均一水平浸透場における熱輸送解析
●日本に棲息するメダカ2種の生理学的差異および遺伝的性判別に関する研究
●環境放射線モニタによる長崎市内における放射線量率の地理的分布
●コンプレッションウェア着用が暑熱環境下での運動中の体温調節反応に及ぼす影響
●大村湾における貧酸素水塊の発達とアカクラゲの分布との関連
●エアロゾルに含まれる天然放射性物質と安定元素の濃度の関係
●メダカ臀鰭上の性ホルモン受容体発現と二次性徴発現の関係に関する分子生物学的研究
●モルフォメトリーに基づく北海道産アユの地域個体群の形態比較
●モルフォメトリーを用いたアユ外部形態の地方差に関する研究
●オオシロカゲロウの発生モデルを用いた卵の孵化パターンと一斉羽化記録の比較
●カモ類を対象とした汎用的な捕獲手法の検討
●有明海奥部において貧酸素水塊形成を駆動する有機物分解過程の解明
●越境大気中の多環芳香族化合物の測定及びその濃度から算出した健康被害のリスク
●非繁殖期におけるカンムリウミスズメの移動様式の解析
●稲作に関する環境教育ツールの開発
●塩生植物アッケシソウの根圏における必須微量元素マンガンに対する生理応答特性
●夏期のオフィス環境において室内気流が作業効率に与える影響
●培養細胞に対するミカン果皮に含まれるフラボノイドの増殖抑制効果
●長崎県におけるPM2.5濃度と降水量の関係について
●葛根抽出液経口投与がラット学習記憶能に及ぼす影響評価
●ホスファチジルセリンがストレス負荷されたラットの発達に及ぼす影響の比較検討
●長崎で栽培されるイネ2品種の収量と品質に対する高濃度CO2の影響
●アルスロバクター属細菌のトランスポゾン挿入変異株におけるマンガンバイオミネラリゼーション特性の解析
●アユの生息/非生息が河川生態系に与える影響の解明
●長崎に生育する樹木の葉に沈着した粒子状物質の量と金属組成の地域間差
●緑藻カワアオノリの塩分濃度別成長条件の再検討
●下水処理排水による性ホルモン遮断効果に関する内分泌学的および分析化学的研究
●九州西部地域における地震の発震機構解のコンパイル
●最終処分場雨水調整池のpH中性化方法(その1)
●チゴガニの鉗脚運動筋および心臓の電気的活動と各種行動との関係
●クリーンエネルギー自動車とそれらの普及予測に関する調査研究
●奥雲仙田代原における草本植物・木本植物の種多様性と開花フェノロジー
●地下水汚染地域の土壌を用いた主要成分の溶出カラム実験
●長崎県沿岸域に出現するクラゲ類の食性解析
●環境調和型精密有機合成を志向したデザイン型キラル触媒の創製とその応用
●エストロゲン様物質濃度とマハゼの生態影響を指標とした九州内と島原地区の河川の対比
●長崎県におけるサシバとノスリの利用環境の比較
●島原半島の地熱の成因に関する研究
●有感地震の発生状況にもとづく橘湾の最近の地震活動
●同温度のアイススラリー及び液体の摂取が体温調節反応に及ぼす影響
●緑藻ヒメボタンアオサの手熊海岸における海出しの試み
●最終処分場雨水調整池のpH中性化方法(その2)
●植物のオゾン耐性に効果を及ぼす有機化合物の合成と物性
●我が国における100%自然エネルギーシナリオを作成した研究の紹介
●長崎県対馬における温泉水の起源および流動機構の解明
●UAVを用いた植生調査及びノスリの採食環境解析
●ロボット及びハイスピードカメラを用いたチゴガニのウェービング行動の解析
●新規キラルスルフィド触媒を用いた立体選択的ブロモラクトン化反応
●東南アジア域における過去気候と将来気候の降水変化の解析
●醤油諸味由来の耐塩性乳酸菌におけるDL-アラニン生産性に及ぼす温度条件の影響
●九州内における原子爆弾由来の放射能の分布
●異なる水温下での高濃度人工炭酸泉下腿浴が心拍変動に及ぼす影響
●水酸基を有する二官能性キラルスルフィド触媒を用いた複素環化合物の精密合成
●福岡県における水文環境の変遷とその要因解析
●学習記憶能を評価する新規装置の開発に関する研究
●河川中の易分解性と難分解性の医薬品類濃度比を用いた汚染源の特定方法の検証
●フタホシコオロギの嗅覚学習に対するニテンピラムの影響
●好塩性細菌ハロモナスにおける炭素・窒素比率の異なる最小培地中での適合溶質生産特性の解析
●長崎市野母崎海岸における18年間の海藻フロラの変遷
●有明海北西部における腐植物質と植物プランクトンの分布
●硝酸塩添加による海面処分場埋立層の有機炭素削減の向上
●奥雲仙田代原におけるミヤマキリシマの保全活動の効果の検証
●チゴガニのウェービング同期に対する抗うつ剤およびネオニコチノイド殺虫剤の影響
●ブドウポリフェノール類レスベラトロールの雌性マウス学習記憶に及ぼす影響評価
●越境大気汚染物質のミジンコ繁殖毒性影響に関する研究
●九十九島パールシーリゾート付近の海浜環境における顕花植物の種多様性
●環境調和型有機合成反応のためのキラルオニウム塩触媒の合成
●琉球石灰岩の溶解要因と溶解速度についての実験的検討